

P.082上
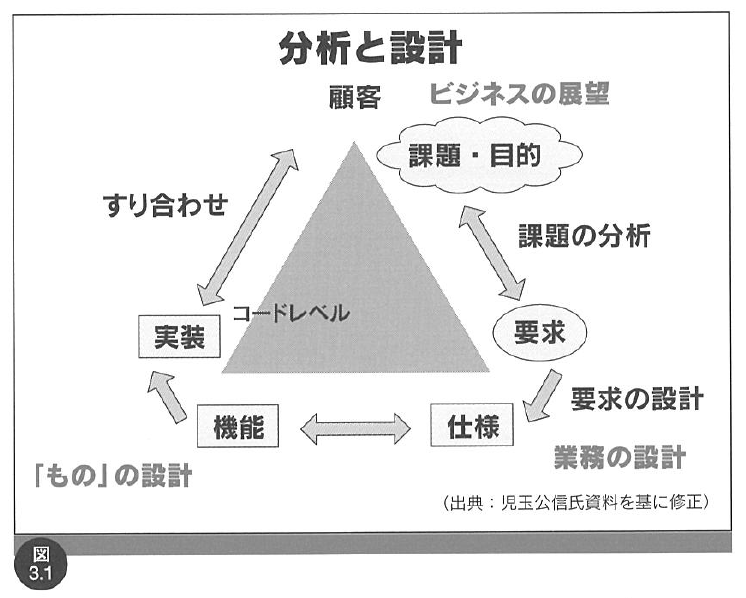
ソフトウェア開発べは何度も分析と設計が行われる
P.082中
この授業では各技術の位置付けを学ぶ。
より実用的な技術については各自が必要に応じて学ぶ。
P.084上
関係者全員が喜ぶシステムを作れるか?
P.084下
↑は難しい。なので先人の知恵が必要。
P.085中
P.086上
理想を言えば、顧客のビジネスを深く理解した上で分析すべき
P.086中~
↑は難しいのでSSMというものが考えられた
P.087中
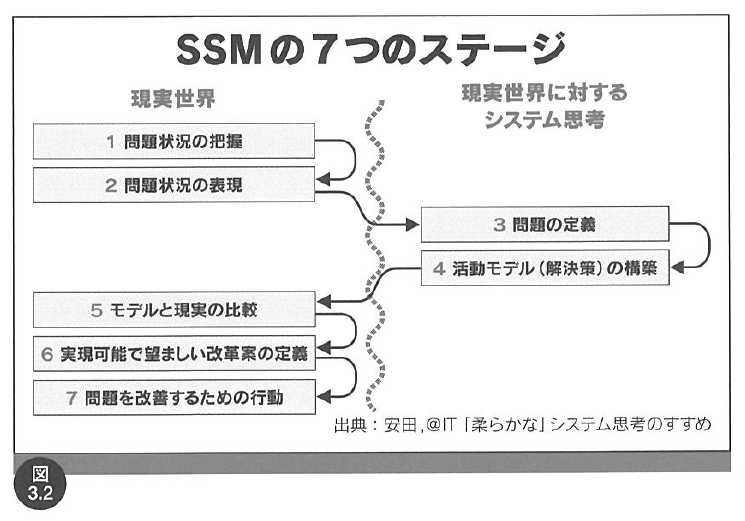
(break: No.43, No.36)
P.089上
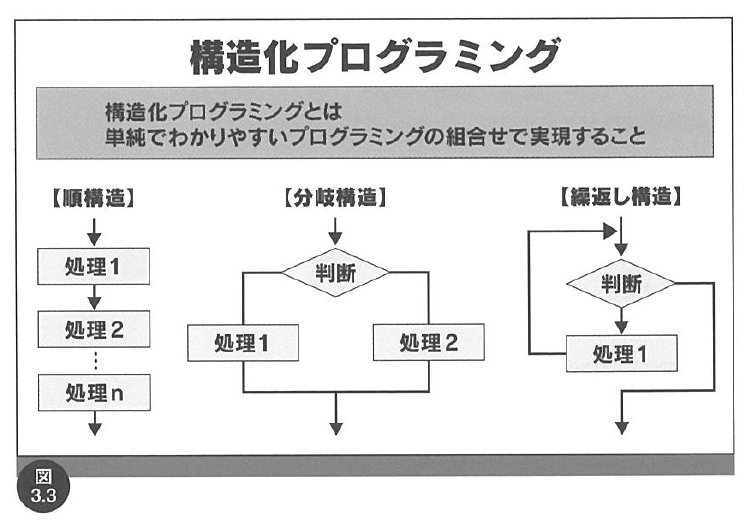
順次・選択・繰返し で表す
P.089下~
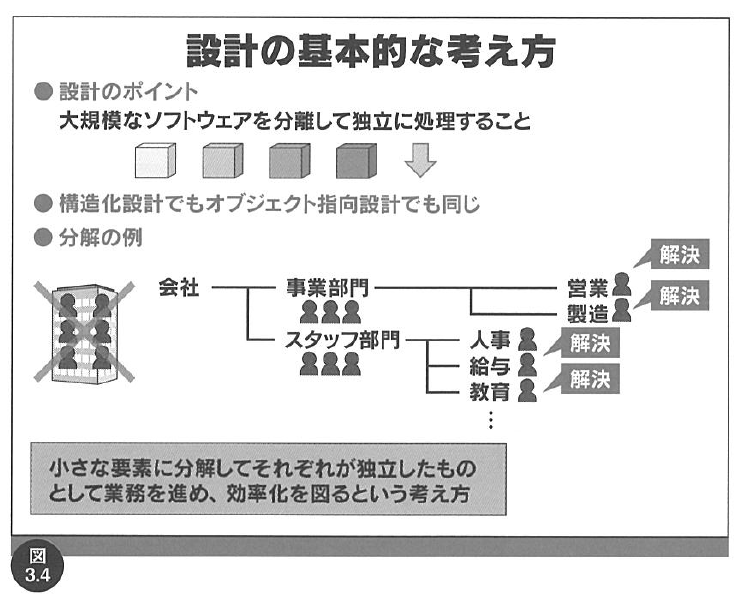
P.090中
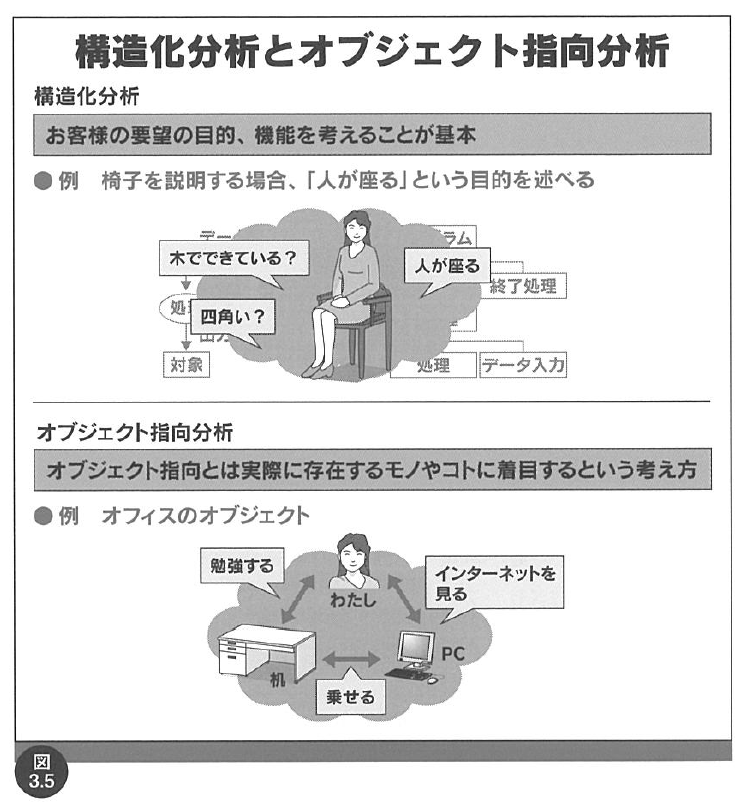
複雑な要求を分析する際には何らかの手法を使うべき
P.091下
P.092上~
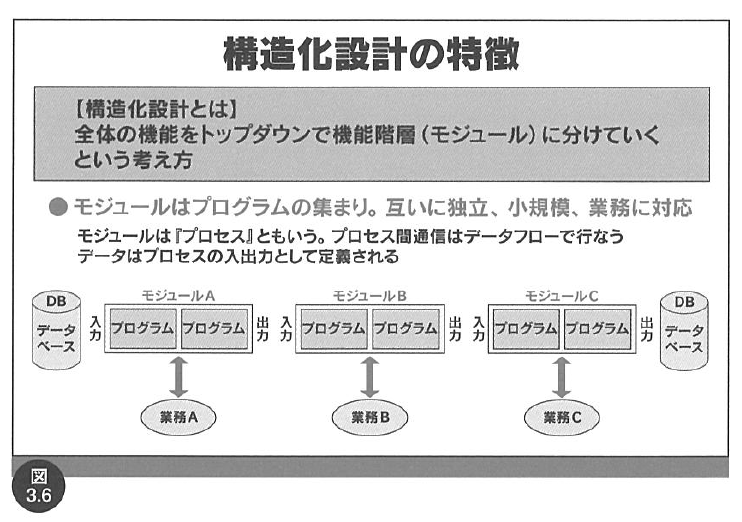
P.093上
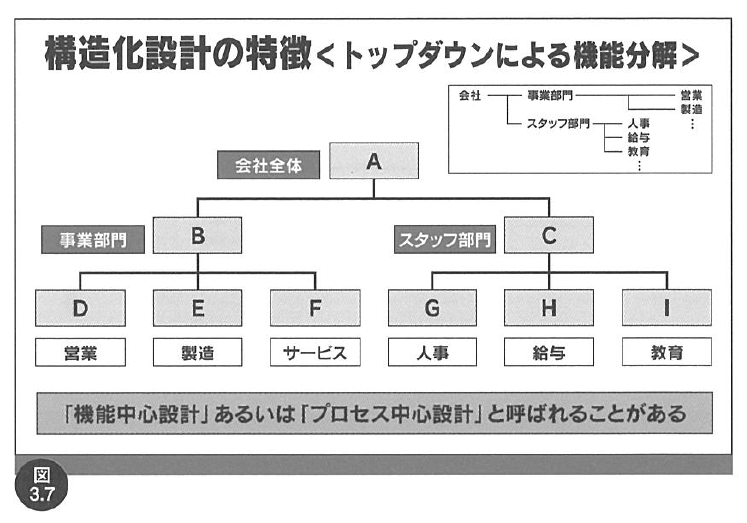
P.093下~
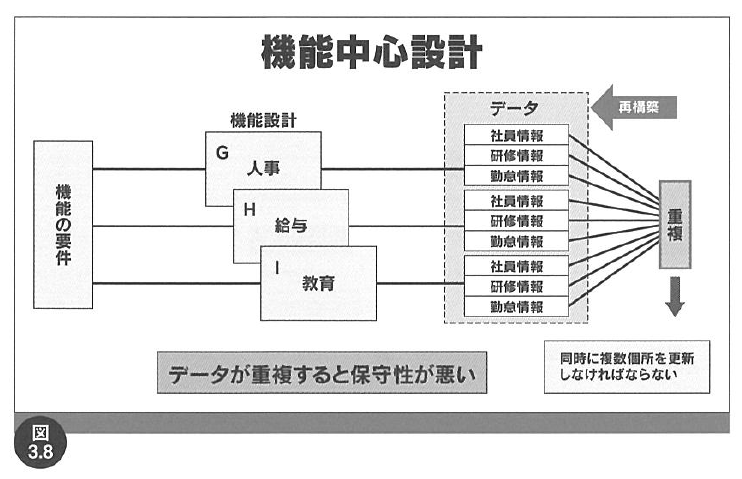
構造化設計ではデータの重複が発生しがち
P.095中
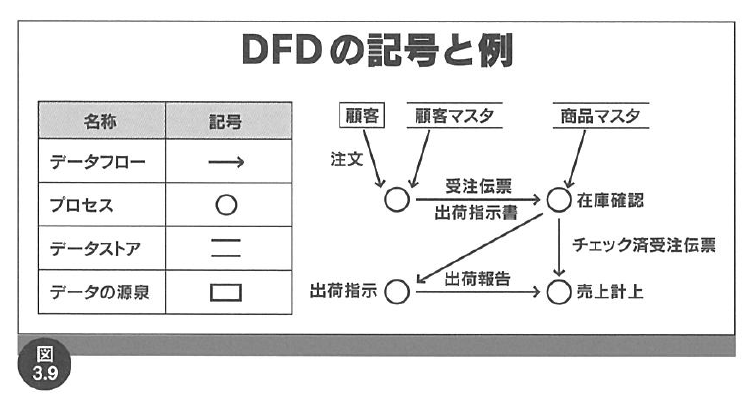
データに注目した表現
P.096上
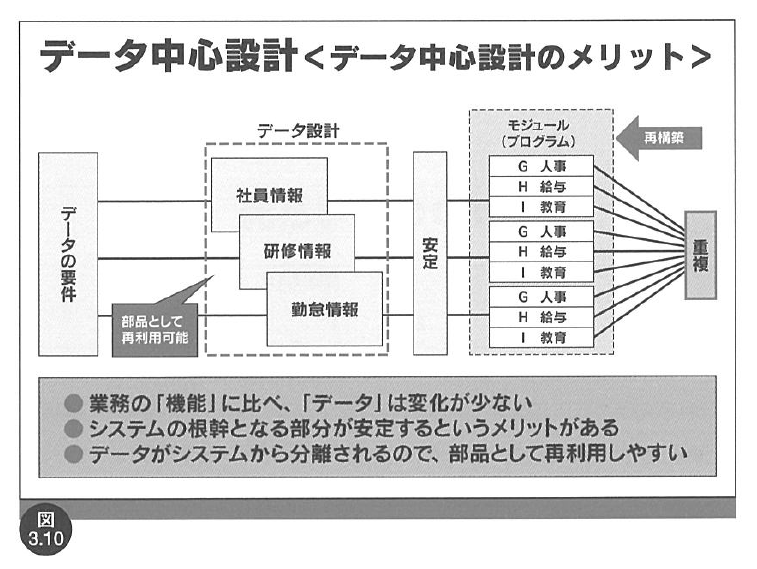
構造化設計ではデータ重複の問題があった
→ データ中心設計
P.096上
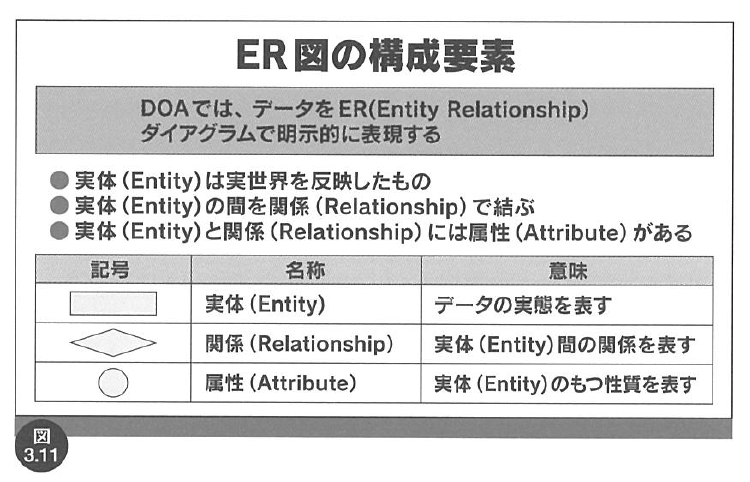
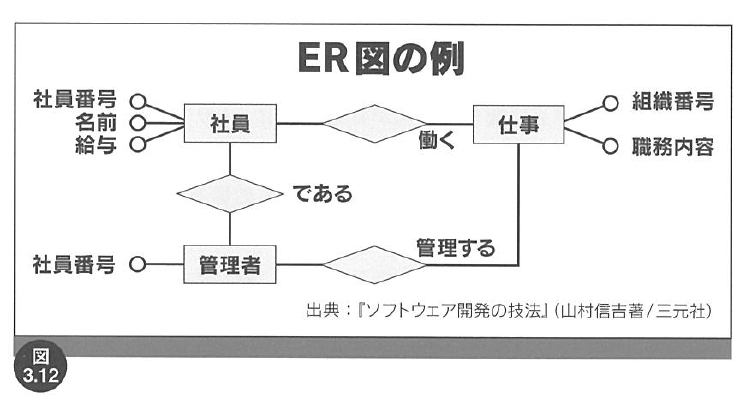
P.098上
データベースを設計 → 処理を設計
P.098上
データ中心だと…
- 変更に強い
- 顧客に説明しやすい
(closing: bouncy)
教科書(図はすべてこちらより引用):
鶴保征城,駒谷昇一著 “ずっと受けたかった ソフトウェアエンジニアリングの授業1” 翔泳社